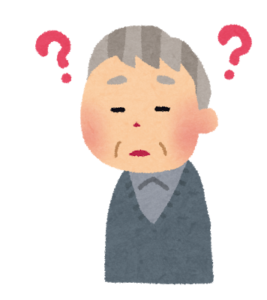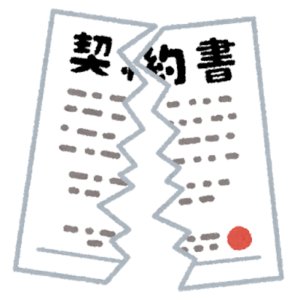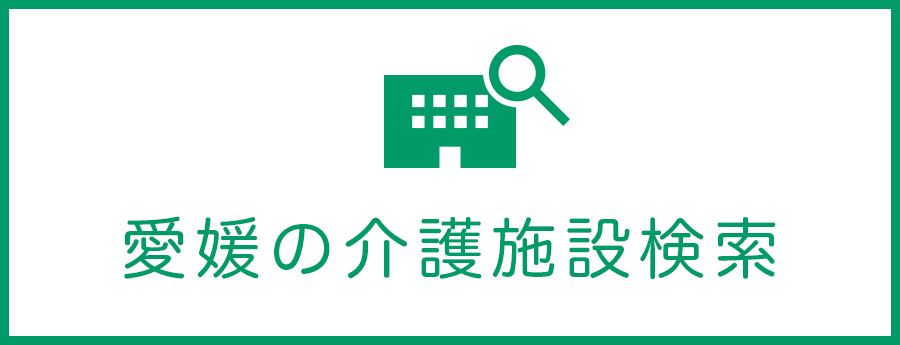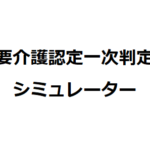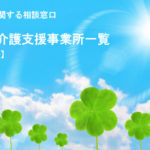2019.04.24今月のメディカサイト特集
いざという時、成年後見制度よりも使いやすい!「家族信託」について知っておこう!

「あれっ?おじいちゃん、最近、ちょっと変かも・・・??」
2025年の日本における65歳以上の高齢者のうち、
認知症を発症している人は「5人に1人」
という厚生労働省の予測があります。
その数、なんと730万人!!
平均寿命が延びるに従い、認知症になる可能性も高くなってきます。
厚生労働省では、2015年1月より「新オレンジプラン(認知症施策推進総合戦略)」を策定し、7つの施策の柱に沿って認知症対策を進めています。
(1)認知症への理解を深めるための普及・啓発の推進
(2)認知症の容態に応じた適時・適切な医療・介護などの提供
(3)若年性認知症施策の強化
(4)認知症の人の介護者への支援
(5)認知症の人を含む高齢者にやさしい地域づくりの推進
(6)認知症の予防法、診断法、治療法、リハビリテーションモデル、介護モデルなどの研究開発およびその成果の普及の推進
(7)認知症の人やその家族の視点の重視
いよいよ認知症は他人事ではなくなってきましたね(汗)
さて、認知症になると、日常生活が送りにくくなることはもちろんなのですが、
家族にとっても別の意味で困ることが発生してきます。
民法上、認知症が発生すると、本人は「意思能力のない者」として扱われてしまいます。
そのため、様々な契約行為が結べなくなってくるのです!
例えば、以下のことができなくなります。
・不動産の建設・売却・賃貸契約
・預金口座の解約、引出し
・生命保険加入
・子供、孫などへの生前贈与
・遺言書の作成
・養子縁組
・遺産分割協議への参加
・株主の場合、議決権の行使
いわゆる「資産の管理や活用」ができなくなってしまうのですね。
自分自身で活用することも、家族への相続対策のための取組みも、できなくなってしまいます。
たとえ契約を行ったとしても、意思能力がない人の契約行為は「無効」、もしくは「取り消せる」ことになっていますので、後々のトラブルの原因となってきます。
具体例を考えてみます。
ある方が認知症になってしまい、
介護施設に入居することになったとします。
しかしながら、現預金があまりありません。
年金は国民年金です。
でも、自宅という不動産を所有しています。
この場合、家を売ったり、貸したりして、現金収入を得ようとしても、認知症ですので民法により契約行為ができません。
そのため、自宅を売却して、介護施設の入居費用や生活費用を得ることができないのです。
では、生活保護を申請しようと思っても、不動産を所有しているため申請が通りにくかったりします。
(自宅に住み続ける場合は確率が上がりますが、施設入居の場合は、売却が優先されやすいです。)
ちなみに、同様の私の親族のケースでは、生活保護の申請ができませんでした。
もちろん、家の売却もできないままです。
別のケースとして、遺言書を作成して、家族のこれからの対策を行おうとしても、
民法第963条
遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない。
という法律のために、遺言書を作成することもできません。
そこで、現在、活用が増え始めているのが、成年後見制度です。
愛媛県では、
司法書士会が行っている、公益社団法人 成年後見センター・リーガルサポート えひめ支部
社会福祉士会が行っている、権利擁護センター ぱあとなあ愛媛
といった団体が、後見人としてサポートされています。
後見人に、資産を管理してもらえますので、例えば、認知症であることを狙った違法契約等から、資産を守ってもらうことができます。
また、日々の生活や介護サービスの利用のためのお金も管理してくれますので安心です。
しかしながら、成年後見制度は、高齢者(被後見人)の「資産を守る」ための制度のため、
・家の売却を行って現金を得ることはできない
(資産を減らすことになるため)
・生前相続や贈与を行って、資産を次世代に継いでいく対策を行えない
というデメリットもあります。
そこで、最近、注目されているのが「家族信託」という制度です。
「信託」とは、「信じて託す」と書くように、「信託」は、「自分の大切な財産を、信頼できる人に託し、自分が決めた目的に沿って大切な人や自分のために運用・管理してもらう」制度。
(一般社団法人 信託協会ホームページより抜粋)
以前は「商事信託」というものが基本で、「免許」が必要な制度でした。
平成19年4月30日に信託法が大改正され、「民事信託」として、家族等が「免許不要」で活用できる制度となり、とても使いやすいやすくなりました。
家族が行う「民事信託」のことを、「家族信託」といいます。
少し、難しい話になりますが、信託に置いては「委託者」「受託者」「受益者」という3者間の取り決めが必要です。
(1)委託者は受託者に財産を委託する
(2)受託者は受託内容に従い財産を運用・処分する
(3)運用・処分によって得た財産や利益を受益者が受け取る
わかりにくいので、具体的にしてみますと、
一般的(本人のために資産を活用)
委託者:父親、受託者:長男、受益者:父親
相続対策(子などへの相続対策として資産を活用)
委託者:父親、受託者:長男、受益者:長男
というイメージです。
今回は、
一般的(本人のために資産を活用)
委託者:父親、受託者:長男、受益者:父親
で考えてみます。
先の事例で考えてみます。
ある方が認知症になってしまい、介護施設に入居することになったとします。
しかしながら、現預金があまりありません。
年金は国民年金です。
でも、自宅という不動産を所有しています。
この場合、家族信託を行っておけば、
父親の自宅を、長男に委託しておくことで、認知症になった後でも、自宅という不動産を売却して現金化したり、賃貸に出して定期収入を得ることができるようになります。
受益者、すなわち、その利益を受けるのは父親ですので、売却費用や、賃貸収入はすべて父親のものです。
長男が自由に使うことはできませんので、兄弟間の争いの原因にもなりにくいですね。
また、父親が他界した際にも、生前に信託口座に預金を移しておけば、口座凍結を防ぐことができますので、葬式費用等、当座のお金として利用する事が可能です。
日本の家族信託は、世界で最も「自由がきく信託」だそうです。
そのため、委託者である父親の、様々な意向を組み入れることができます。
公正証書にしておくことで、死後の相続トラブルの回避にも繋がります。
ただし、
家族信託も「認知症」になってからでは、取り組むことができません。
「認知症」になる前に、取り組むことが必須なのです!
信託の内容は、父親が健在である限り、何度でも書き換えることが可能ですので、時期に応じて見直していくこともできます。
「家族信託」という制度。
知っておくと、とても便利な制度ですよ!
まずは、気軽に「家族信託」について、お話を聞いてみましょう!
※ちなみに、家族信託は「信託銀行」に相談しても無意味ですのでご注意くださいね。
【家族信託の専門家はこちら】
くらしの窓口
愛媛県松山市湊町4-11-19 (クリックでgoogle map)
0120-953-472 (クリックで電話)
権利や財産を守る身近な仕組み「成年後見制度」を活用しよう!
↓↓↓